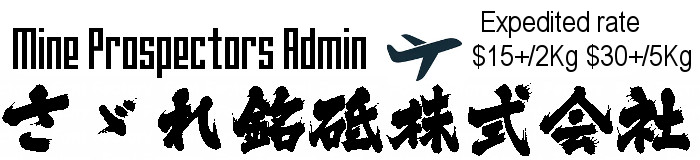inquiry  review, public Q&A(0) review, public Q&A(0)
|
100切より上の型を挙げます。
山城國山本流型呼称で参ります。
梱り(こうり)あたりの入り本数を数字表記とし一取引この本数でやり取りし、概ね梱り当たりの取引価格は同じ感じでした。
昭和の取引形態なので、新時代では砥石産業維持存続の為に廃するべきを責務とします。
これは例えば、百切が四本と少しで二十四切と等価であるが市価では3,000vs6~25万円以上。
梱価値の等比でいうならば、3,000vs12,500円からだから、百切り扱う梱コストから見れば百も二十四も同じ梱コストにも関わらず、4.8から20倍以上ほど利鞘が見込めます。
更に、鍛え済原石出しでは超絶に圧縮された単価となるので、大半が原石出しと僅かな製品出しでは、命懸けで山と対峙していたにも関わらず、すればする程困窮し、健康を害し、山城國砥石産業は有史以来の最大の境地に立たされたことと忍ばすには居れません。
梅ケ畑の砥石展示場には、昭和中期から平成かかり迄の帳面など見るとが出来、時が進むとともに梱単価の烈しい下落に涙を禁じえません。
概ね表の大きさですが誤差アリ。
相の大きさだと、七十切型とか五十切型と呼ぶこともあります。
幅や丈が出ていると、八十切幅広とか四十切八寸丈とか呼ぶこともあります。
㊟二十四切は尺長(しゃくなが)という異名を持ちますので、読んで字のごとく30㎝の長さがあるといしと連想しがちです。
しかし下記の表の大きさに留まる大きさで218mm程度です。
由来はこの型を取るなら尺の長さを持つ端正な原石が必要になってくるためです。
型の最高峰が二十四切長尺、尺長八寸、尺長長尺(しゃくながちょうしゃく)でありどれも同じ型を指し単に八寸丈を採用し縁起物でもあります。
|
|
型 Size
| 単位 mm
| 鎌砥
| 40± x 130± | 100
| 55 x 160 | 桟60・80・40
| x 180,195,205 各型の30-50巾程度と大きく巾足らず
| | レザー | 80 x 135 | | 80 | 60-65 x 180 | | 昆布 | 100± x 140± | | 60 | 70x195 | | むらかみ | 80-90 x 180± 包丁に適すよう村上考案型 | | 40 | 75 x 205 鍛え落ち・抜けあり・薄め
| 30
| 75 x 205 基本八つ角 本山で24以上厚
| 24(尺長)
| 78 x 215 ㊟24長尺(尺長八寸)は概ね八寸丈を言い型の最高峰
| 大判
| 90+ x 230
| 八寸丈
| x 240 漢字文化圏に好ましい末広がり八寸 贈答やゲン担ぎ
| がつ板
| 産地加味して極めて厚板 故に丹波國で実寸あってもこれに能わず
| 以下不定形
|
| こわり
| 小さく薄く割ったもの 共名倉や指砥石として肌の仕上げなどに
| 落ち
| 挽き落ちから採りなおし 動機から自ずと上である傾向大
| | こっぱ | 出来形 主に1Kg 以下 ここでは百切以下もこちらに仕分ける
| | 原石 | 大きな不定形面付、鍛え済そのままの場合もあり
|
|
|
|
|
|
|
|