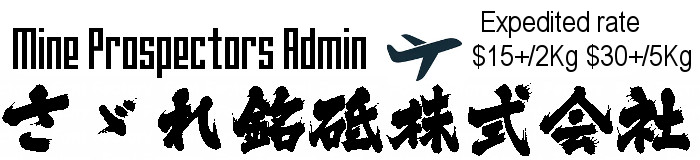|
通常葉理・層理の節目で熱水鉱床をくぐるときの熱水変成で溶け出たSiO2が再析出するので、葉理・層理に沿う形で出来るとおもわれる。
結合度の脆弱さ→圧力の下落起きやすいという考察。
一方、単にカネのある時代はチャート質が多く堆積したものといえるのも当然。これが成立するためには必ず葉理・層理に沿う形でないといけない。
つまり、粘板岩とカネは連続時間軸で紡がれたという考え方。
|

|
この見本のように、葉理を斜めに切ってカネが斜行貫入していると、カネは時間軸に倣う形で出来上がるという考え方が成立しない。
プレート移動の外力で、葉理を斜行横断する力が働いてクラックが入ってしまった、もしくは単に同様に斜行横断する肌やつけが出来てしまった。
この結合度脆弱性に沿ってSiO2が再析出してしまった。
皮肉にも外力で出来上がった斜行で分断された石をふたたび波の鍛ェでは気づけないほどつよいボンドの役割を担うに至る。
斜行で内包的にあるカネに気付けなくて挽いてしまって今にいたる。鋸は大ダメージ!
と考えるのが妥当ではないかと思う。
後天的変性によりカネが出来上がったという証拠写真とも考えることが出来て、余剰なSiO2が溶け出て種々の条件下で集まって再析出して、例えば石の硬さが柔らかになるとかより砥石としての適正を得ることが出来たのではなかろうか。
母材たる珪質粘板岩の出来が早くて、カネはあとから。たとえばハワイあたりから京都に乗り上げるまでにできたきたと考えうる。
|

|
http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/geology/tisitugensho/nessuihensitu/nessuihensitu.html
参考サイト
時として王水を超える勢いのある溶媒として暴れている?
確か水は300度300気圧くらいで臨界点 Critical pointを迎え、気層でも液相でもないし、気層でもあり液層でもある状態に至るみたいです。
液体の強い溶解能力と気体の拡散性を併せ持つといわれ、SiO2→ガラス質に近いものなんかでもどんどん溶かして散り散りにさせてしまうのです。
おならは時を過ごせばやり過ごせるのは拡散性の恩恵そのもの。なので、悪知恵を働かせればすかしっ屁をして動かないで時がたつのを待つのです。
おならが液体と仮定して鼻のあたりについてしまったら想像する事さえはばかられますよね!
私たちの生活圏での水は塩をとかせば辛いし砂糖もたくさん溶かせますからジュースのみすぎはカロリー過多でいけません。
気体であるCO2でもたくさんとかせますのでぱちぱちの泡泡のビールが今日もおいしいのです。
最後まで読んでくださってありがとうございます。
ここに準じる面白い見本の画像等あれば寄稿いただきますよう願います。
|
|