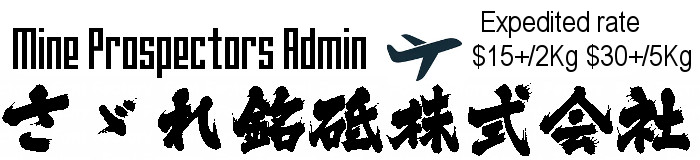inquiry  review, public Q&A(0) review, public Q&A(0)
|
ゴリゴリやってなるべく一様な条痕の連続体を刻む作業ともいえる研ぎ。
付いた条痕を真上から二次元的な平面で俯瞰しかできないにもかかわらず、あれこれ判断したくなる人の目玉では見えない世界について考えます。
1.広く浅いU断面条痕形状は乱反射。つまり雲見映え。
2.狭く深いV断面条痕形状は一様な反射。つまり鏡見映え。
1-.柔い研磨剤は被切削材硬度と拮抗してしまうため、これに依存して条痕形状が大いに変わる。
2-.硬い研磨剤は、1-と相反。
1.=荒い 2.=細かい と判断してはいけない。
1と1-は鍛接線を明瞭とさせる。
2と2-は鏡面深度向上しやすいが、被切削材硬度依存による条痕の入り方に差異ができにくいため、一様な鏡面とかになりやすい。
Tip モース硬度表において
雲母や人の爪が2
長石6
石英7
アルミナ9
カーボランダムなど9.5
ダイヤモンド10
水焼き日本工具鋼で6-7
天然砥石の種たる研磨剤は石英由来
硬度数値の差異が大きいほど深く大きく切削することができる。
差異が小さいと相反。
青棒で知られる三価クロム(毒なのは赤の四価クロム)のステアリン酸で吊るした緑の研磨剤は6ですごく細かい。バフで鏡面つくりといえばコレという定番ものだけど、意外に刃物の部位ごとの硬度差による鏡面深度が変わってくるので、ダマスカス鋼材の仕上げや、単に和包丁を手軽に鏡面に仕立てたいときに、軟硬におけるコントラストと鏡面深度も両立しやすく好きな人には受けが良い。
うんと柔らかいちょんまげ時代産の良く下げができた包丁鉄の一部だと天然砥石が荒く感じることがある。なので超絶粒度そろえやすい砥石探しには純鉄を当ててみてると、切れる切らせるにはあまり差し障らないとおもえるところだけど砥石性能の深淵の一端を覗き見ることができる。
一般工匠具+天然砥石の組み合わせで素敵な鏡面深度達成を成功体験として抱く方が純鉄付に対して同じ達成度を追い求めてしまいがちだけど、これは鼻の穴にすいかを入れてみようと試みるようなことなので考え直しましょう。
鏡面深度はがっつりがっかり下落するものの、お上品な雲、鍛接線が浮き上がって見えるなどが体験できれば美術点において万々歳。
純鉄は工業的には電解鉄ともいわれ、トリプルか?カルテッドナイン?の純度の鉄ですごく柔らかく、一番永久磁石になりにくい鉄で爪で押してもやんわり跡がつくほど。
この性質上スピーカーの真ん中の震える鉄心に使われるので、ポンコツが出た際に取り出しておくと、銘砥眞眼のひとかけらを手にできたとも言えます。知識を得たことによる実質無料眞眼ゲット。良い響きです。
更に、う~~んと柔らかいアルミを研ぐと閉口したくなるような目視上の条痕が!手短に軽く一円玉研いでみます?
これは柔らかすぎて眞眼には不向きで、手軽にがっかりしてみたい人にお勧め。
青棒で仕上げたアルミ素地の古典的な鏡の雲っぽい感じが出来上がる理由もここまで読んでいただけたなら簡単に想像できると思います。
なので、石だけの選定で、被切削材はわからないし、謎練度であるなら例えば鏡面深度には大いに幅があり。
1/3の条件しか固定されていない状況で先のことが見えたなら、神様に職替えできる?
|
|
高雄の珪質粘板岩天然砥石の砥石として含包される研磨剤自体は、人造の名だたる高粒度のものよりずっと荒いとおもう。
研ぎ摩擦でフレーク状に剥離が起こって、そこの研磨剤はある程度指向性をもって配列してる。硬度が低い研磨剤だし、基剤は長石や雲母といった鉱物なのでさらに破砕しやすい。
泥漿を巧く操って注水を抑えて破砕を繰り返していくと、かなり細かいフレークを造り出すことができる。
これは、石の性能、刃物の種類と研ぎ手の練度で大方決まる。
粒度の定義は網目を通過できる出来ないの粒で仕わけたものであるけれども、扁平で高さのないものと高さがある立方体や直方体が同じ網で仕訳けられるともいえ、高粒度になるほど研磨剤の形状は如何に?と気を配らないといけないし、高粒度の数字に縛られてしままうことを疑問にかんじるはずです。
扁平基剤で研削能に劣り浅くUの字断面条痕かつ破砕しやすいという、荒~中砥の掛かりくらいでいうところの致命的な欠陥は、高粒度においては替え難い利点に転ずるということは容易に想像できると思う。
|
|
|
|
|